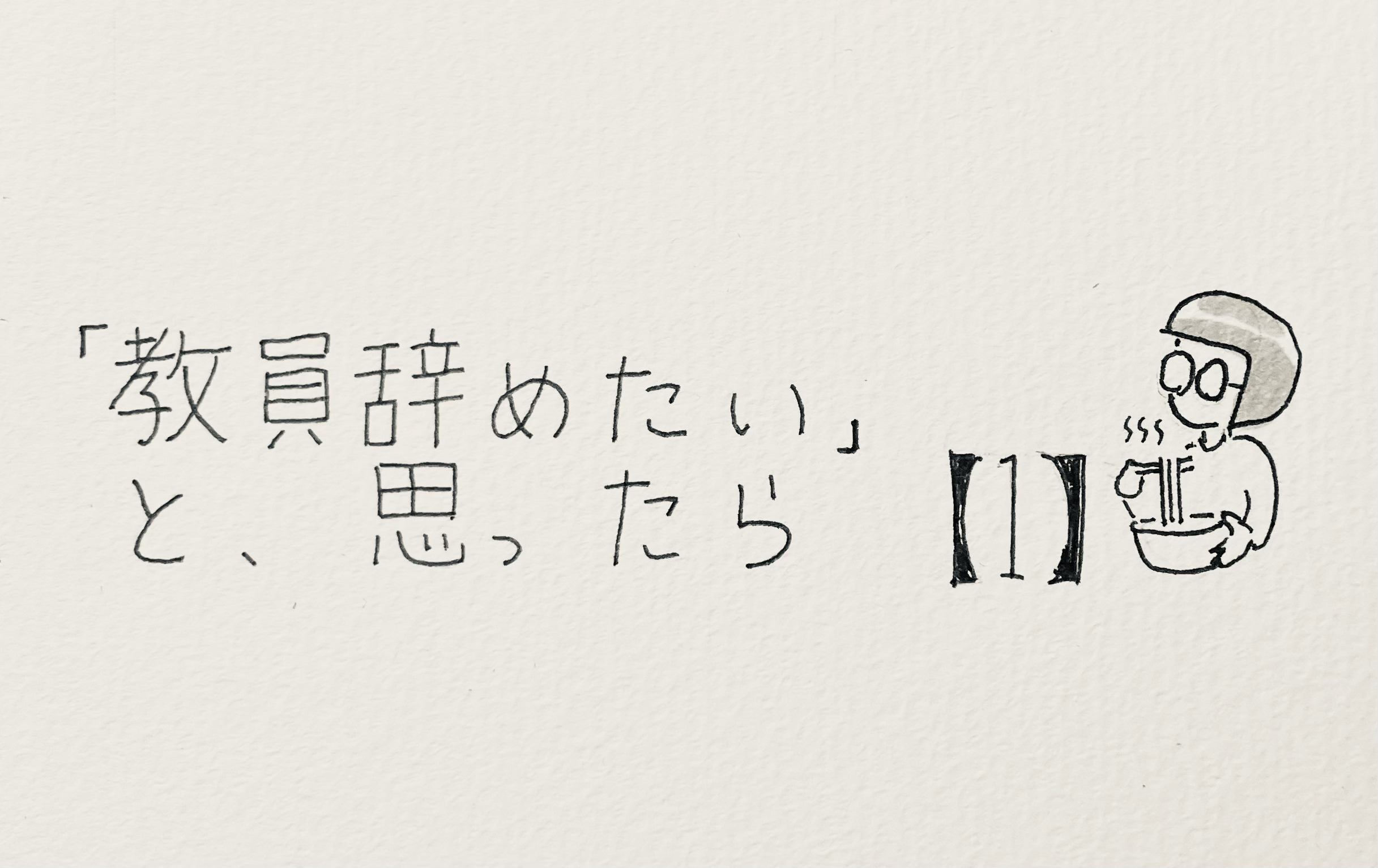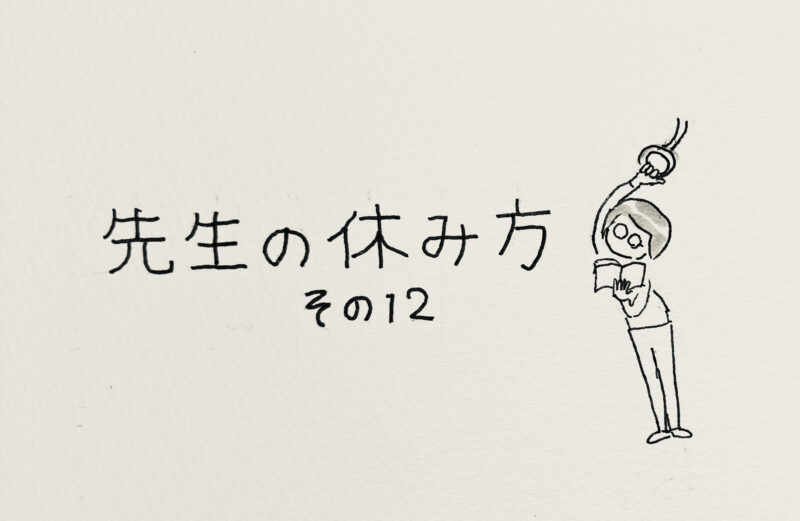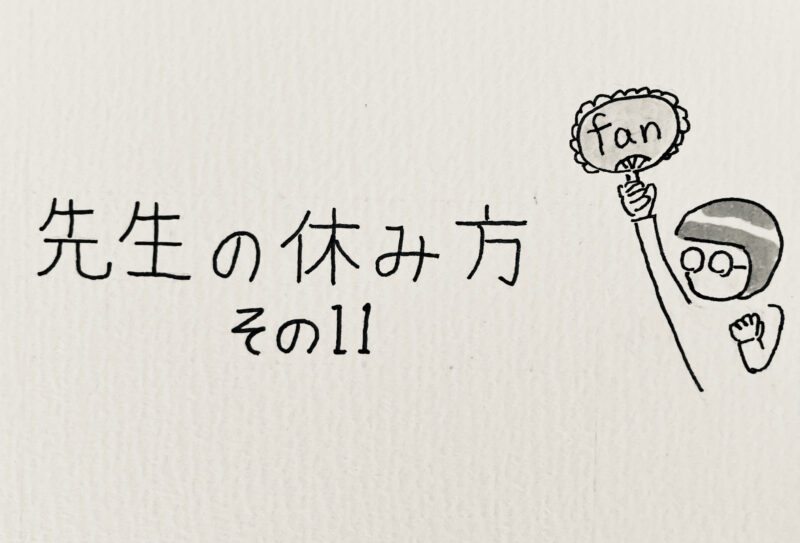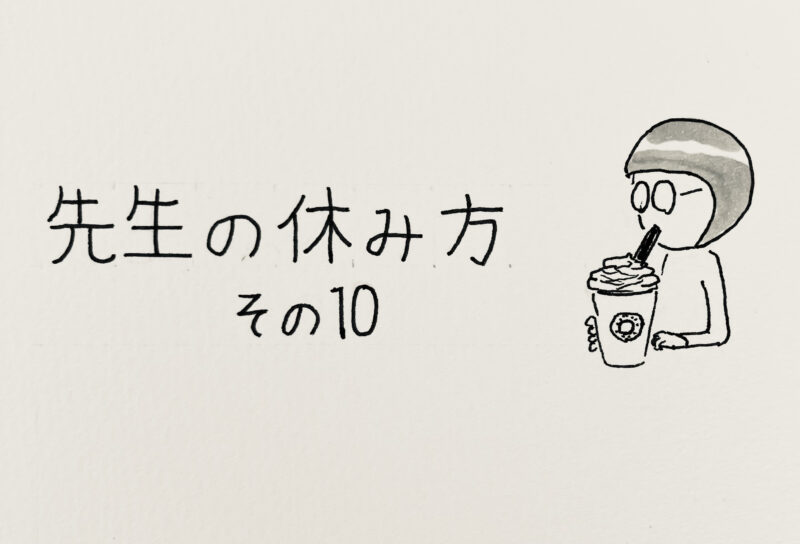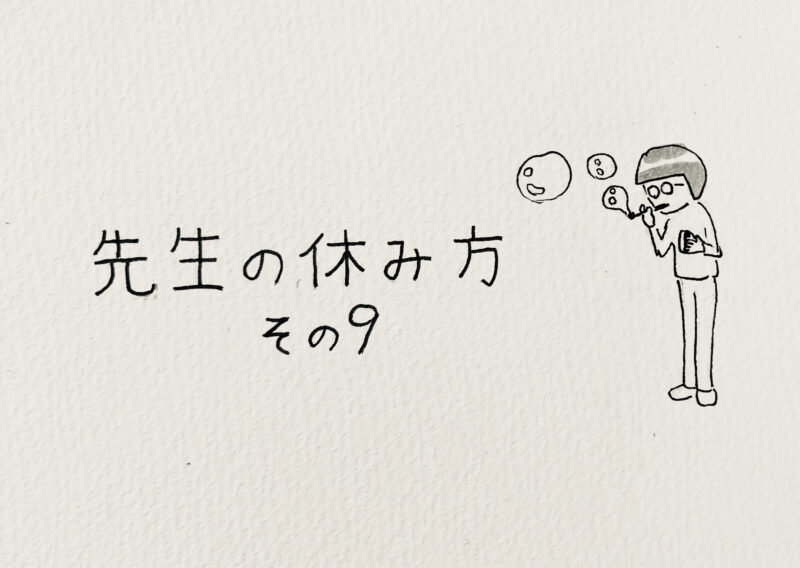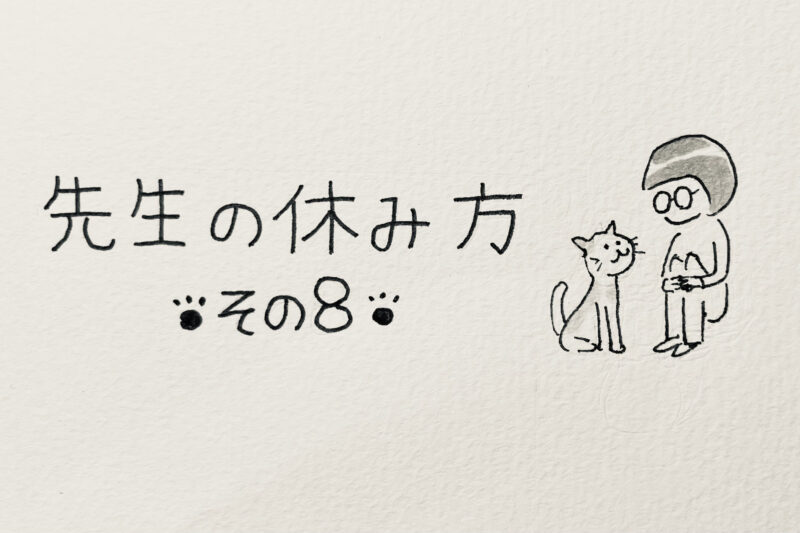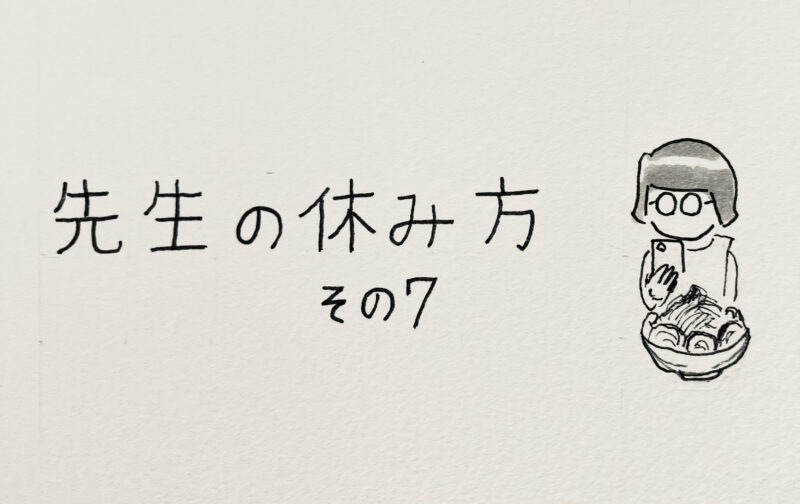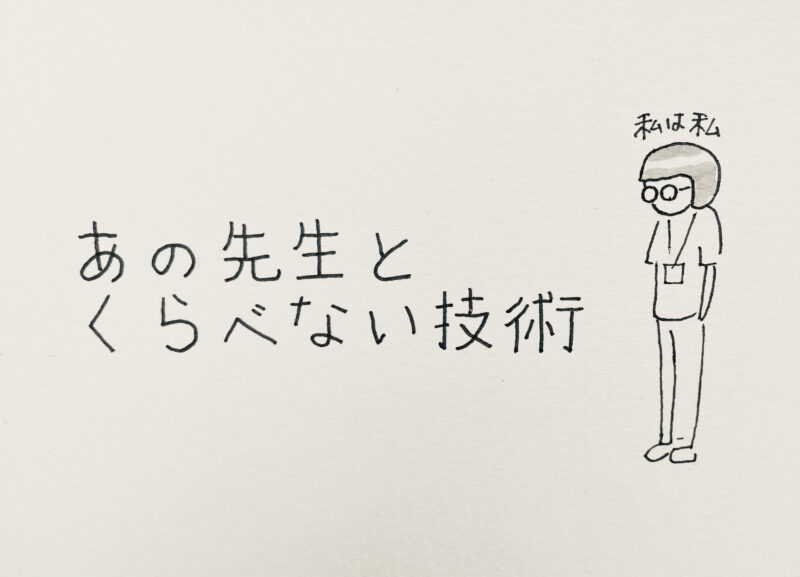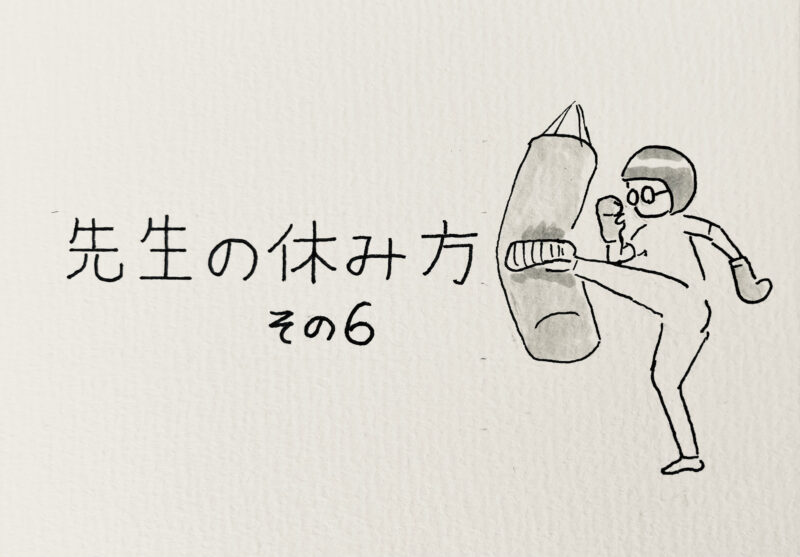はじめに
自分のSOSに気付けない
私は教員時代、2度の休職を経験しました。1度目は45歳の時。2度目は47歳の時。2度とも援助希求できずにバーンアウト。同じパターンで休職に至りました。今思えば、様々な前兆が心身に現れていました。しかしそれは、時間が経った今だから気付けること。当時の自分は、他者に対する感覚は過敏になっていたにもかかわらず、自分に対する感覚は完全に麻痺していました。
学校という環境の中で、教員という立場の自分が、自分のSOSに気付くことは極めて困難なことでした。また、自分の危機状況に気付いた時、どのように助けを求めてよいのか、その方法がまったくかわかりませんでした。
今を乗り切るヒントとして
現在私は、教員を辞め、スクールカウンセラーに職を転じています。たくさんの理由があっての転職でしたが、大きな理由の一つに「自分のような理由で辞める先生を減らしたい」という思いがありました。つまり、自分のことを後回しにすることで苦しむ先生を減らしたい、という思いです。怒りに近いその思いは、このブログやサイトを立ち上げた原動力にもなっています。
ここに書く内容は、あくまでも私個人の経験談に過ぎません。ピンとこない方もおられるでしょう。それでも、今苦しみながらも頑張っている先生、「教員を辞めたい」とギリギリな状態にいる先生。そんな先生方にとって、私の経験談が、今を乗り切るヒントとして、少しでもお役に立てたら嬉しく思います。
今回は「『教員辞めたい』と思ったら」の第1回目。「教員は天職」は要注意、というお話です。
「教員は天職」は要注意
休職を経験するまで、私は「教員は天職」だと思っていました。そうした思いは、苦しい状況を乗り切る際、自らを奮い立たせるモチベーションになりました。と同時に、心のアクセルを過剰に踏み続けてしまう原因にもなってしまうこともありました。
子どもからの評価
子どもは正直です。授業や行事など、しっかり準備をすれば、子どもは反応してくれます。つまり、努力の成果は、子どもの反応というわかりやすい形で返ってきます。これは教員にとっての最高の喜びです。子どもからの評価は、自然と「教員は天職」という思いにつながっていきます。
同僚からの評価
私は教員時代、子どもの発言によって展開してく授業が最高の授業だと思っていました。実際、子どもたちも楽しそうに授業に取り組んでいました。そうした授業を実践するたび、同僚からも評価されました。同僚からの評価も「教員は天職」という思いをますます強化させていきました。
子どもが変われば
教員を続けていれば、必ずある現実にぶつかります。子どもが変わると、今までの方法が通用しなくなるという現実です。それでも私は、今までの方法を繰り返しました。うまく行ったときの方法を「あと少し、もう少し」と続けました。しかし、子どもたちははどんどん離れていきました。
分かっているけど、変えられない
方法を変えた方がいいことは、頭では分かっていました。それでもなかなか切り替えられませんでした。自分の成功体験を捨てられなかったのです。今まで通りにいかない焦りが、自分をさらに頑なにさせます。そんなはずはない、と引き返せない状況に自分をどんどん追い込んでいってしまうのです。
相談できないから苦しい
そんな時、誰かに「ああ、もうどうしたらいいのかわからないよ」「もう無理」と言えれば少しは救われるものです。しかし「教員は天職」と思っていた自分がこのような事態になると、恥ずかしいという思いが強くなります。その思いが邪魔をして誰にも相談できない状態に陥りました。
苦しいのは、自分のせいではない
「神村先生、少しお話ししませんか?」そんな時、私を救ってくれたのは、週に1回学校に来るスクールカウンセラーの一言でした。放課後の相談室で、苦しい思いをはじめて言葉にしました。毎日顔を合わせる同僚や家族には言えなかった思いが次々と溢れてきました。そして、スクールカウンセラーからこう言われました。「苦しいいのは、先生のせいではないですよ」と。
脳のせい
「先生のせいではないですよ」「苦しいのは、脳のせいです」「先生は今まで子どもたちが活発に発言する素晴らしい授業をたくさんしてきました」「脳が、その時の喜びをずっと求めているだけです」「脳が、先生を頑張らせてしまうんですよ」スクールカウンセラーの一つ一つの言葉が、こわばった私の心をほぐしてくれました。
こだわりを手放す
脳のせい、と言ってもらったことで、自分の状態を冷静に見つめることができるようになりました。自分には全くない視点でした。自分が同じ方法にこだわっていたのは、「子どもが発言する授業が最高」という思いからでした。そして、その思いの根っこには「教員は天職」という思いがありました。一つの成功経験が自分を苦しめていたことに気付くことができました。
「誰かとつながる」という方法
そして何より、自分の苦しさを打ち明けられたという経験が、気持ちの安定に大きく影響しました。一人で抱え込んでしまっている時、真っ先に必要なことは、誰かに話したり、受け止めてもらったりすることだとあらためて実感しました。当時の私にとって、スクールカウンセラーは週に1度会える相手でした。正直、相談相手の候補ではありませんでした。しかし今となってはその距離感がちょうどよかったのだと思います。
相談するという成功体験
教員を続けていく上で、成功体験は大切です。しかしそれは、評価だけの成功ではありません。誰かに相談するという成功体験こそ教員には必要だと思うのです。教員は、どちらかと言えば相談される側の立場です。その立場や思い込みが、時に自分を追い詰めてしまうことがあります。もし今、うまくいかないな、もう辞めたいな、という思いが強くなっていたら、誰かにその思いを話してみませんか。
誰かとつながる
そんなこと言っても、相談できる相手なんかいない!という方もおられると思います。私も、当時は相談できる相手は一人も思い浮かばず、「みんな敵だ」と思っていたくらいです。そんな時は、自分が安心できる人を思い浮かべてみるのもいいかもしれません。人でなくてもいいのです。ペットでも、推しのキャラクターでも。誰かとつながる経験は、未来のさらなる成功体験にあなたを導いてくれると信じています。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございます。このブログは先生応援ブログです。日々学校現場で頑張っている先生が、隙間時間にサクッと読んでちょっと元気になれる、そんなブログを目指しています。スクールカウンセラー神村でした。