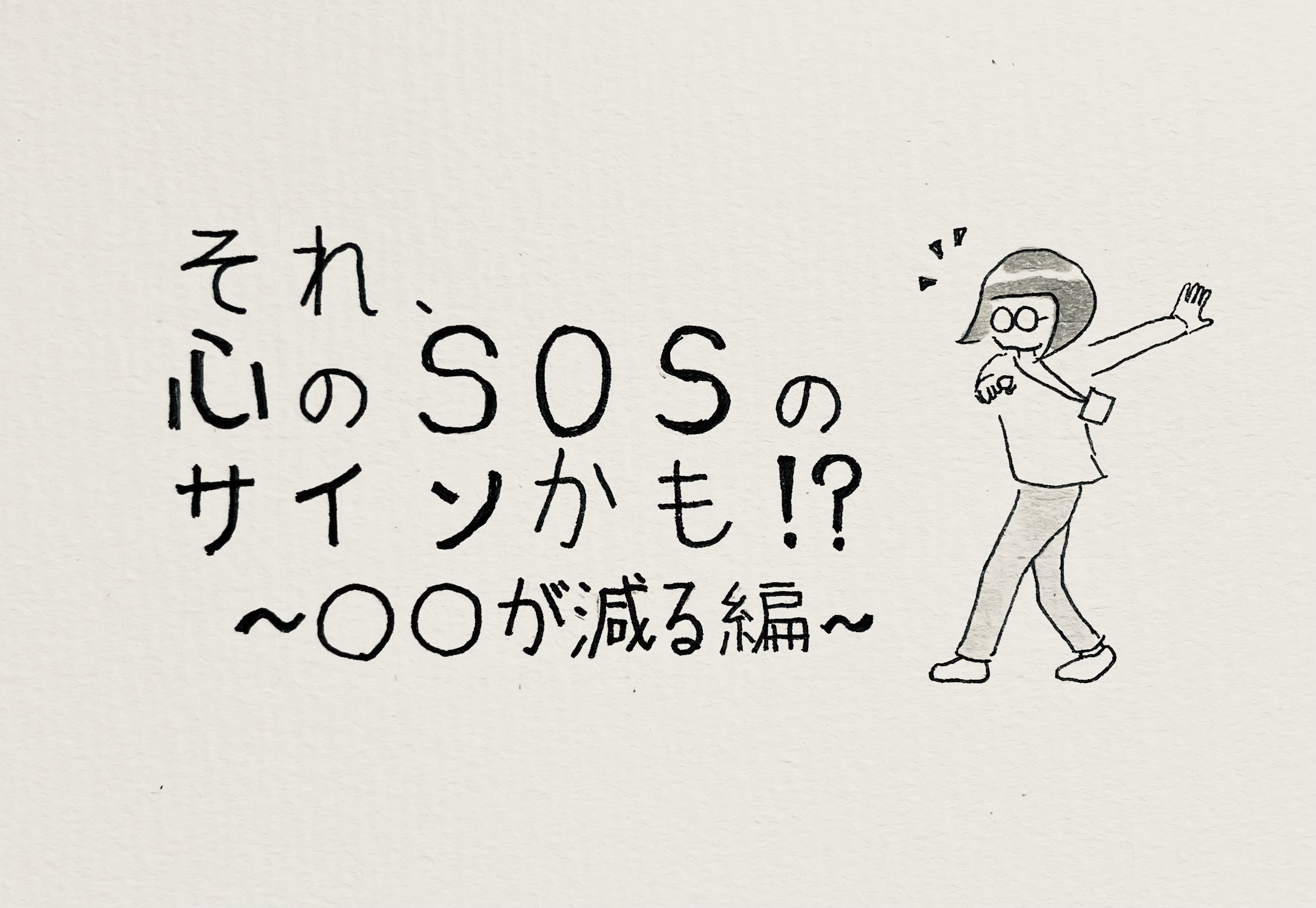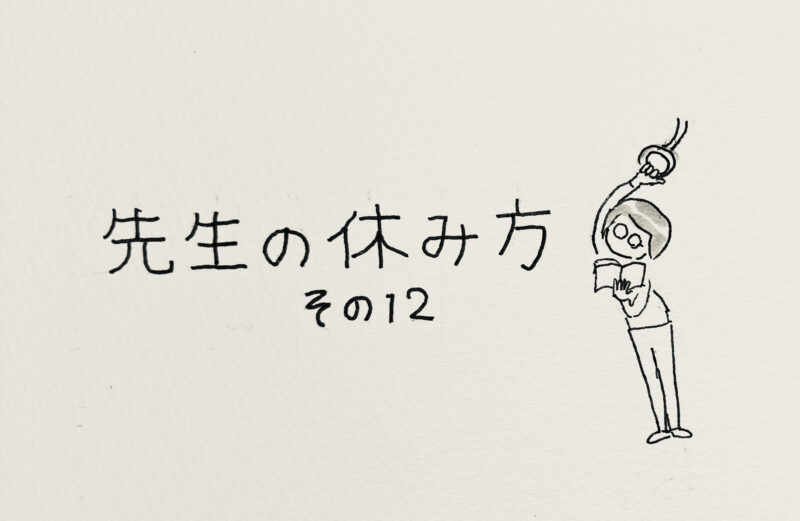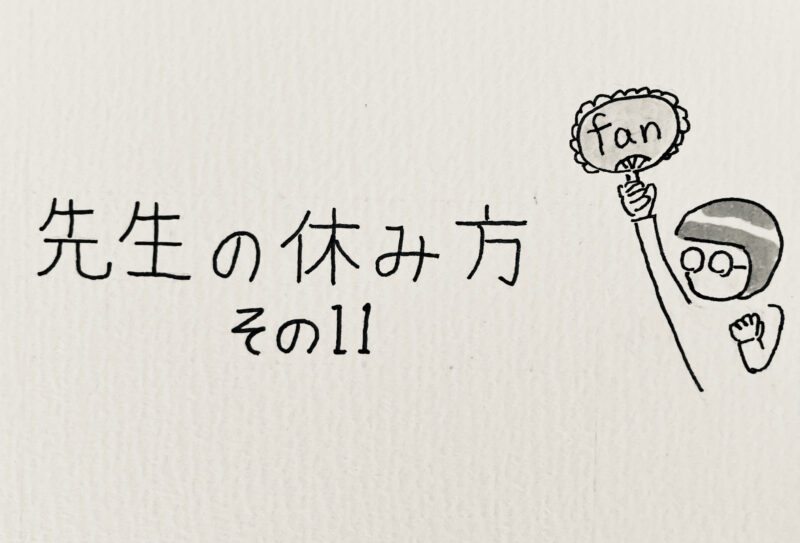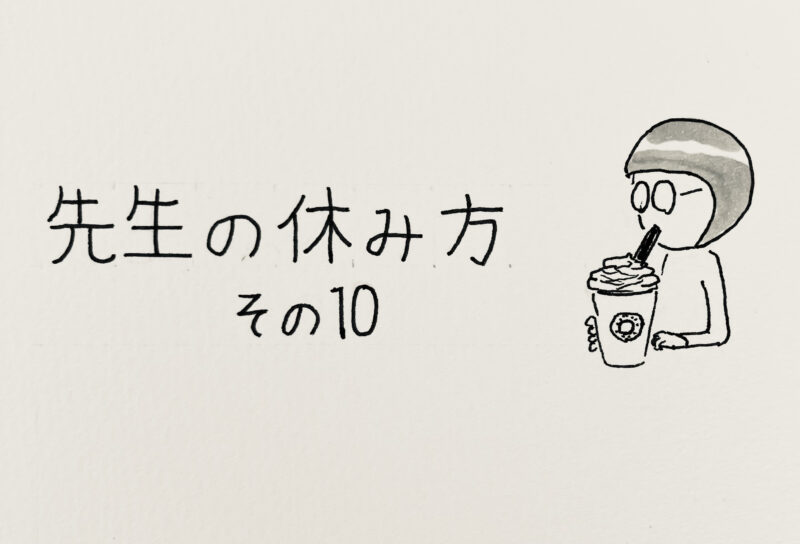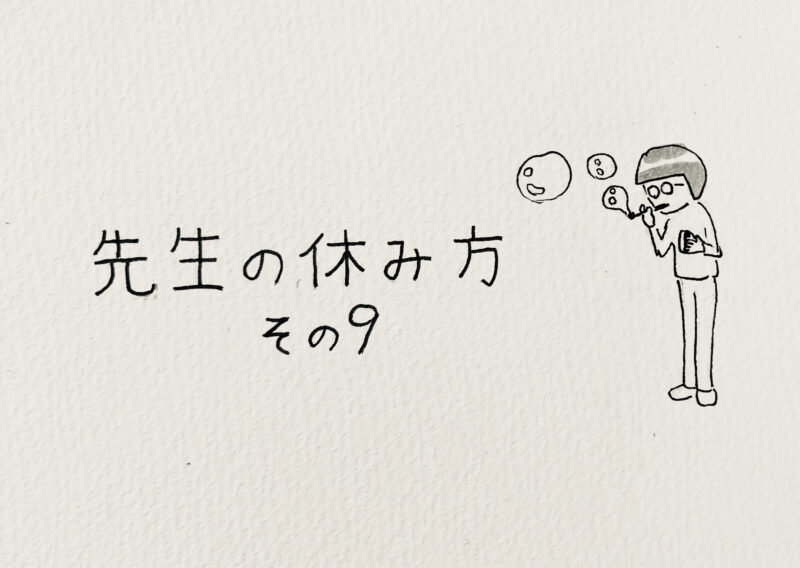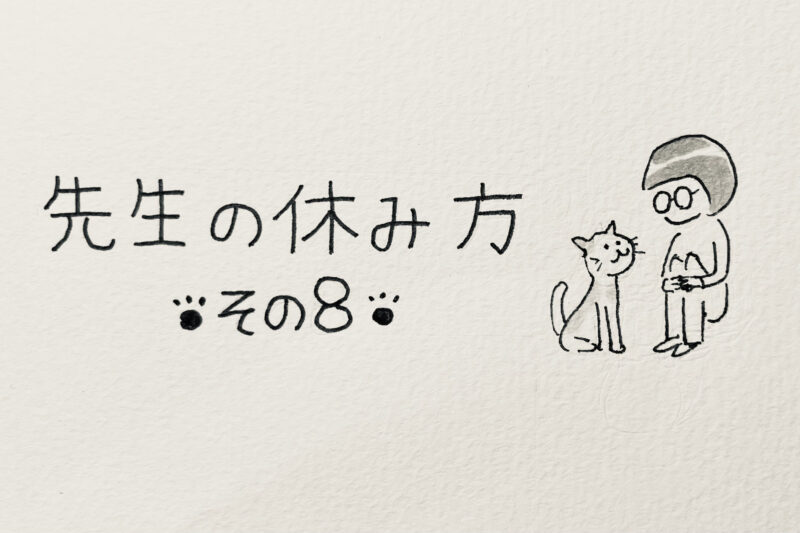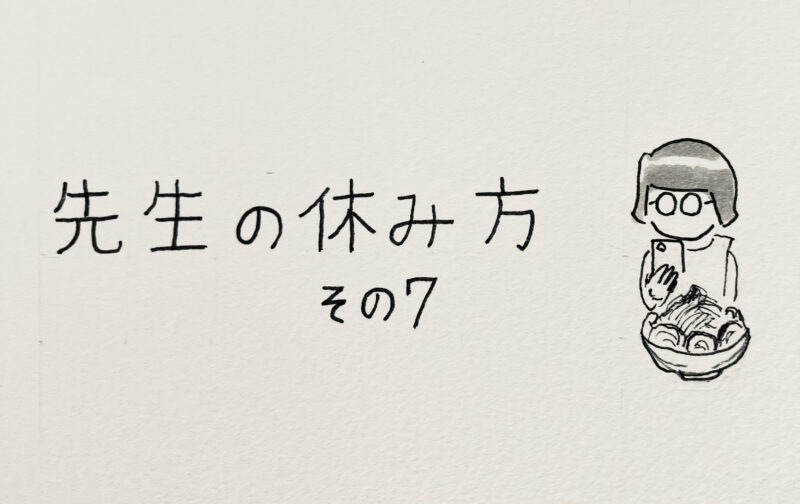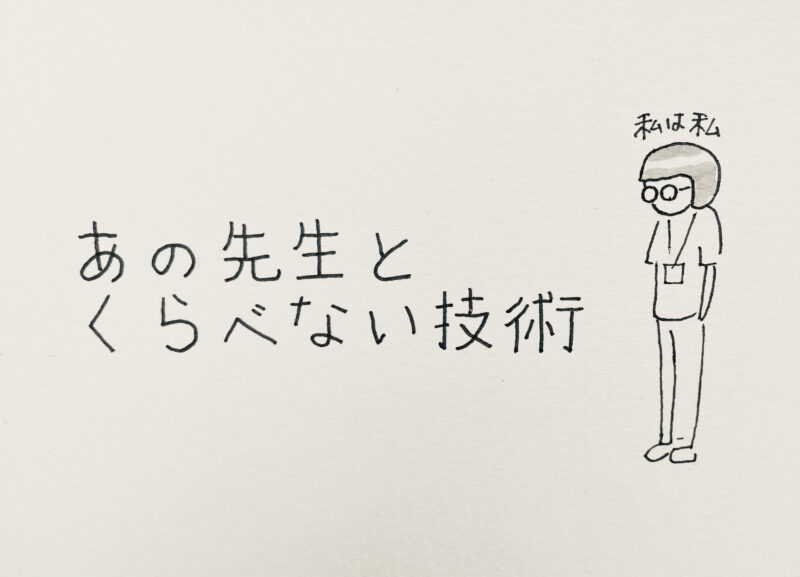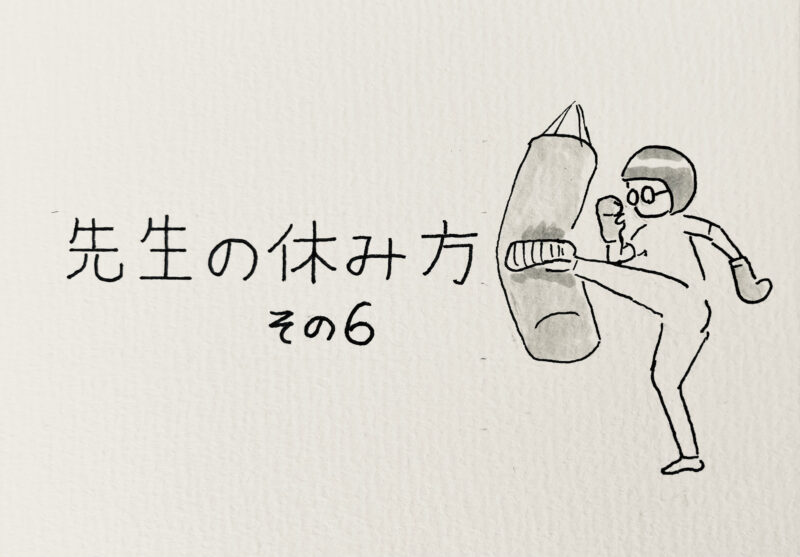他人のSOSにはよく気づくのに、自分のSOSには気づきにくい。そんな先生はいませんか?こんにちは、スクールカウンセラー神村です。教員は、指導者であるとともに支援者でもあります。支援者は他の職種と比べ、被援助志向性(助けを求める傾向)が低いという研究結果があります(水野、石隈1999)。今回は「先生のためのSOSの出し方講座」の3回目。【◯◯が減る】という視点です。ご自分を振り返る際の参考にしてください。
◯◯が減る
いつもの自分と比べて何かが減るという視点は、注意をしないと見過ごしやすいサインです。いつもの自分(食事、睡眠、行動、余暇の状態)と比べて、というのがポイントです。意識的に振り返ってみてください。
子どもの寄ってくる頻度が減る
子どもは先生(大人)を本当によく見ています。先生の表情や立ち居振る舞いにいつもと違うもの(不穏さ)を感じると、子どもは敏感に察知し警戒します。近くに寄ってきません。教員時代、私の教室のデスクの周りには、いつも子どもがいました。しかしある時期子どもが全く近寄らなくなりました。まさに私自身、不調の絶頂期でした。子どもの反応は、時に自分の心の状態を写す鏡となります。
雑談が減る
職員室で仕事以外の話題ができなくなってきたら要注意。仕事に心が支配され始めています。もちろんコミュニケーションが得意ではない人、時間に限りがある人の場合は別です。しかし、もともとおしゃべりが好きなのに、雑談が減っているのであるのなら要注意。一人で仕事を抱え込み過ぎていないか立ち止まってみましょう。忙しい時こそ、雑談。雑談は心の薬です。
水分補給が減る
朝、職員室を出てから給食の牛乳を飲むまで、水分(液体)を全く口にしていない。そんなことはありませんか?今はマイボトルを持ち歩く先生方の姿も増えてきて安心していますが、それでも先生方の水分補給の時間は少なすぎると感じます。教室では、先生の意識は常に外に向かっています。しかしそんな時こそ、水分を体の中に入れましょう。自分の内に意識を向かわせましょう。水分補給は、体と心の潤い補給です。
歩数が減る
例えば授業。机間指導をよくしていた先生なのに、黒板の前にずっと立ちっぱなし。椅子に座りっぱなし。例えば休み時間。いつもは校庭で子どもと遊んでいたのに、教室の机で一人で仕事をしたり。トイレや更衣室でぼんやり過ごしたり。歩数は、心のエネルギーとも連動しやすい数値です。省エネを心がけていないのに、歩数が極端に減っていたら要注意です。とりあえず歩きましょう。
週末のワクワクが減る
日曜の朝、目覚める。「もう明日は学校か」と憂鬱になる。休日なのに頭の中は学校のことばかり。まったく心が休まりません。先生という仕事はやりがいの多い仕事だと思います。一方、終わりのない仕事でもあります。仕事のストレスは、自分の裁量を超えた時、強くなると言われます。本当は休みたいのに、仕事のことが頭に浮かび続ける。それはもはや裁量を超えています。週末は先生をやめましょう。ワクワクを取り戻しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。このブログは先生応援ブログです。サクッと読めて、ちょっと心が軽くなる。そんなブログを目指しています。スクールカウンセラー神村でした。