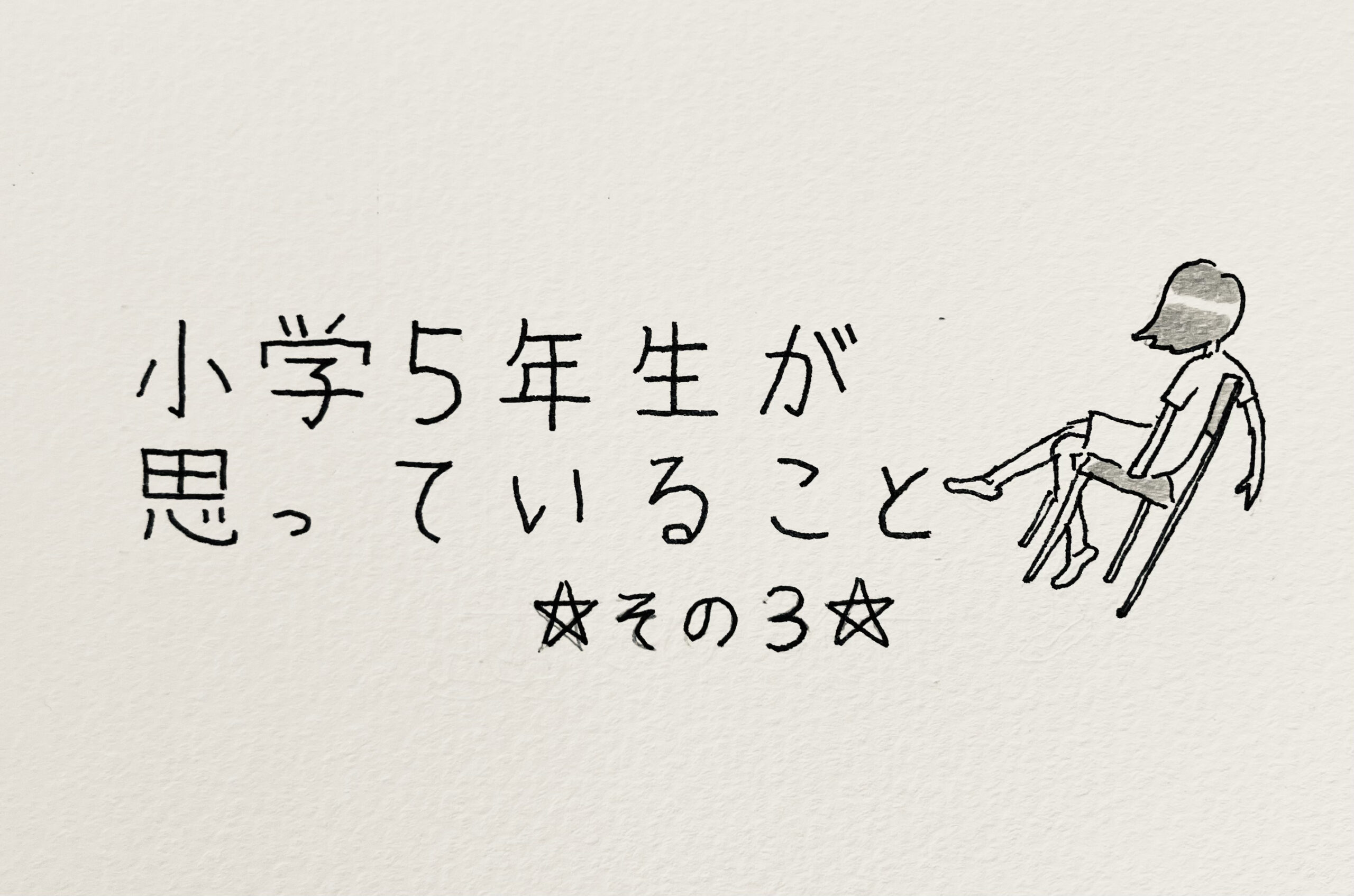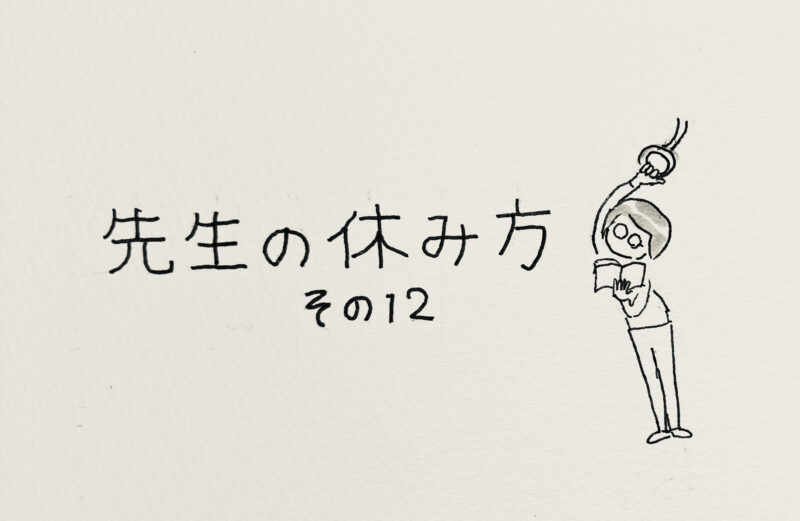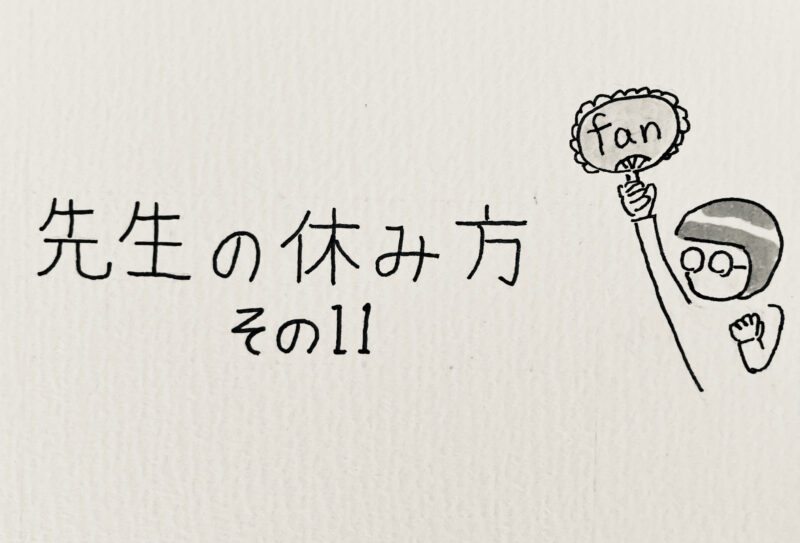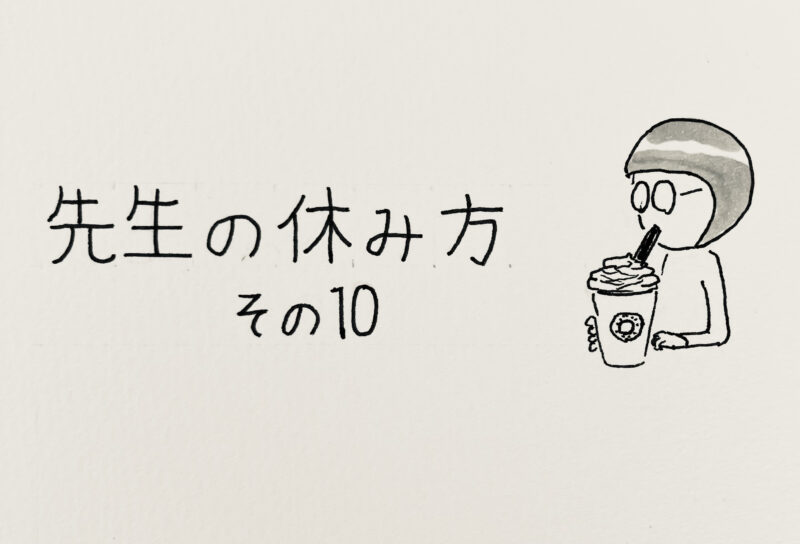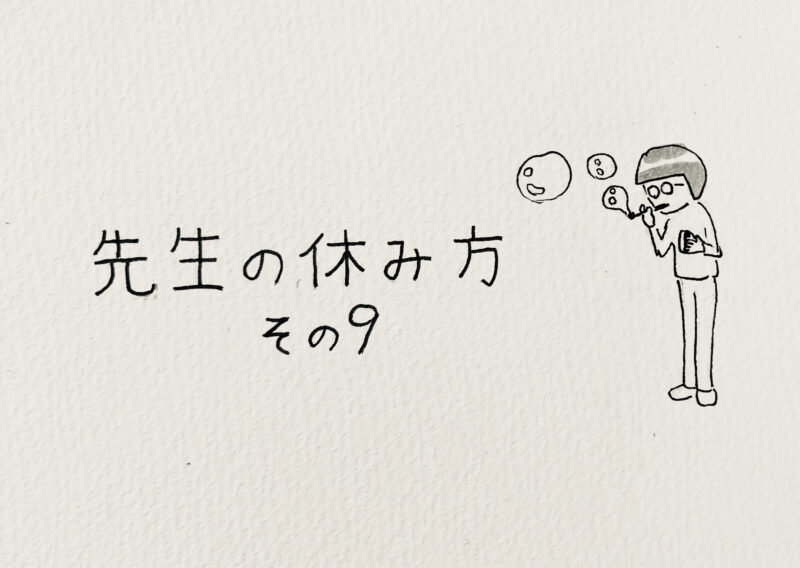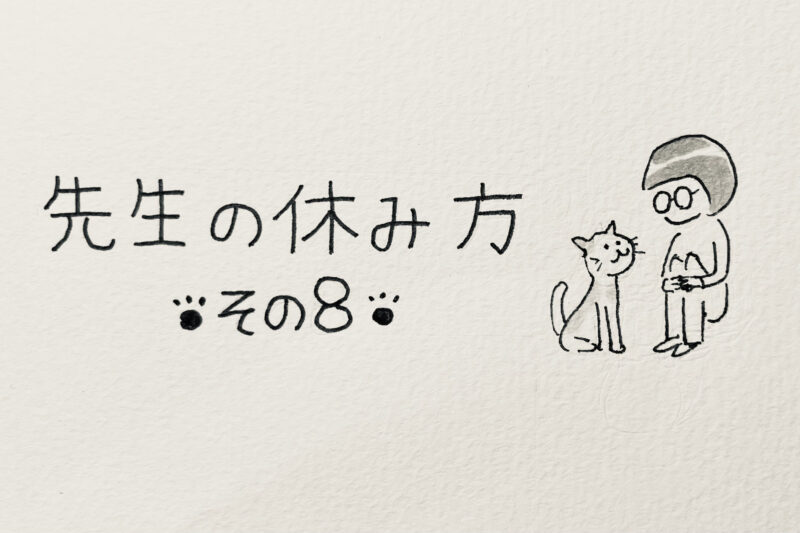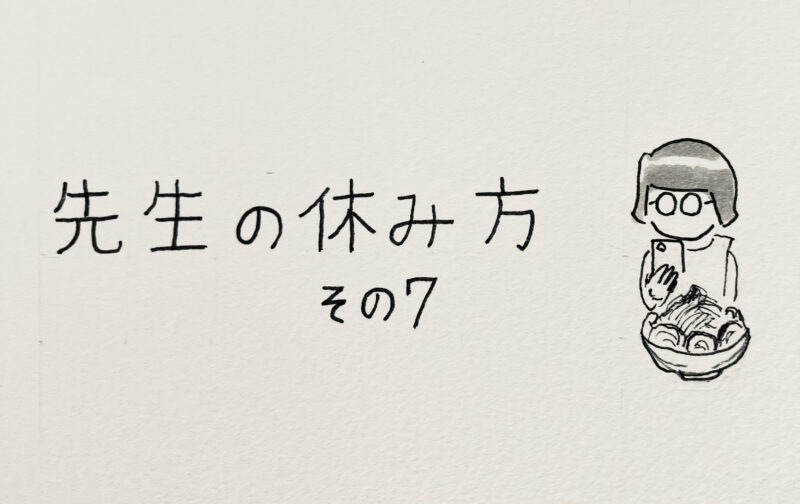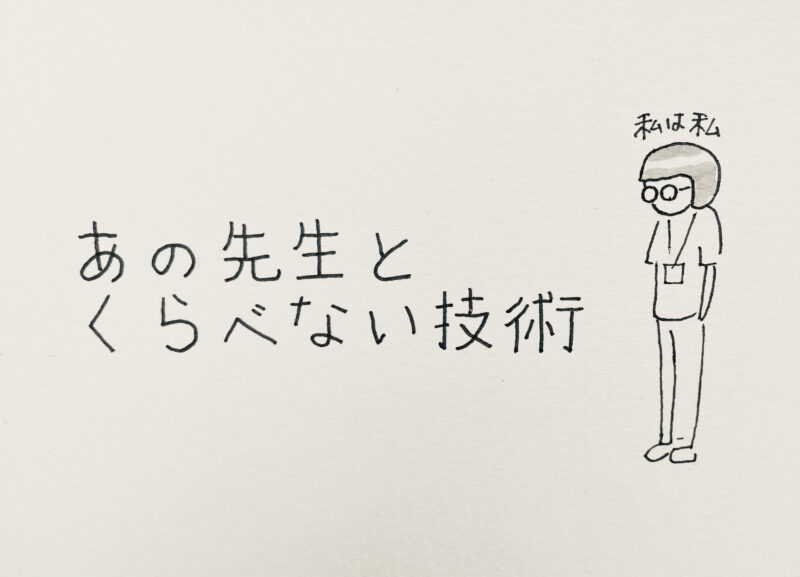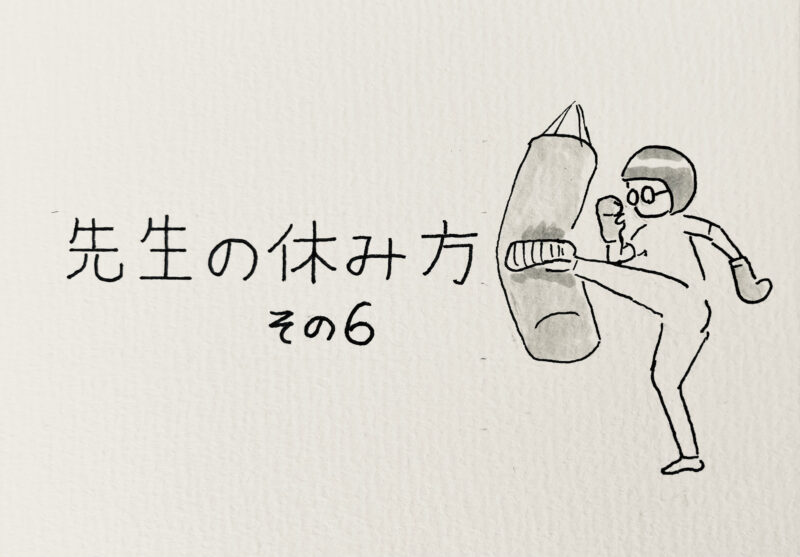思わぬ子どもの一言に、オロオロしてしまったり、フリーズしてしまうことってありませんか?特に子どものネガティブ言葉には、大人の不安をじわじわと煽ってくる力があります。しかし多くの場合、ネガティブ言葉の背景には、言葉の意味とは違う、その子の思い(ときにSOS)が隠れています。もしその思いに注目することができたら、それは大人の余裕になります。そしてその余裕は子どもの気持ちを受け止めることにつながります。こんにちは、スクールカウンセラー神村です。今回は「5年生が思っていること」の第3回目。ネガティブ言葉に隠された子どもの思いについて考えてみます。
●ね
この言葉の意味を知らない子どもはいません。意味を分かって使っています。大人が強く反応することを分かった上で使っています。そのくらいその子は今、感情が高ぶっているということです。悲しさや怒り、諦めや悔しさ…。何に対してそのような強い感情を抱いているのか。そうした視点をもってかかわっていくことを大事にしたいです。言葉の注意はいつでもできます。今必要なのは、その子の「どうしていいか分からないくらい、つらい」という思いを受け止めてあげることだと思うのです。
もういい
この言葉は、大人のイライラを助長します。勝手にしなさい。自分でやりなさい。と思わず言い返したくなります。しかし多くの場合、もういい、は、全然よくない、です。つまり「もういい」という言葉の背景には「見捨てないでほしい」というその子の気持ちが隠れていたりします。子どもが「もういい」と言ってきた時は、とりあえず「そうか」「分かった」といったん距離をとりましょう。時間的・空間的な距離を取ることは、大人の冷静さを取り戻す上でも大事です。そして再び「一緒にやってみない?」などと声をかけてみましょう。大人のほどよいしつこさは、子どもの安心感をほどよく高めます。
あの子だけズルい
どの学級にも特別な支援が必要な子はいます。同時に、そうした子を見て、「ズルい」と言う子もいます。「ひいきだ」「差別だ」と大人を非難してくることがあります。そうした言葉の裏には、自分も助けてほしい、と言う思いが隠れている場合が多いです。しかし、同じ支援を必要としているわけでありません。なぜなら、同じようにしてほしい?と聞くと、多くの場合「違う」と言うからです。つまり、自分も困っていることに気づいてほしいとというサインなのです。その思いを伝えてくれたことに感謝を伝えること。そして何ができるのか考えていくことを伝えていくだけで、その子は落ち着きます。
最後までお読みいただきありがとうございます。このブログは先生応援ブログです。サクッと読めて、ちょっと心が軽くなる。そんなブログを目指しています。スクールカウンセラー神村でした。